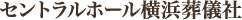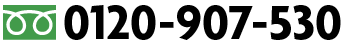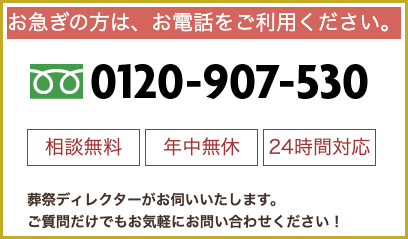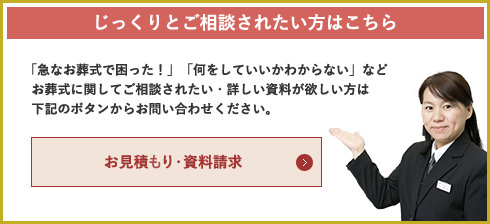神道(神葬祭)の葬儀の費用と流れ
神道(神葬祭)のお葬式とは?
神道の葬式である神葬祭は、故人様を守り神として家に留まってもらうための儀式とされています。 また、神葬祭は神社で行われることはほとんどありません。神道では死は穢れ(けがれ)であるとされていて、神社のような神の聖域に穢れを持ち込むことはよくないとされています。
神道(神葬祭)のお葬式の流れ
私たちは「ご縁」を大切に、スタッフ一同「思い」を込めてお手伝いをさせていただきます。


帰幽奉告(きゆうほうこく)
訃報を聞いたあと、神棚や祖霊舎(それいしゃ、みたまやと呼ばれるもので、仏教における仏壇に当たるもの)に故人の死を奉告し、神棚や祖霊舎の扉を閉じて白い紙を貼ります。

訃報を聞いたあと、神棚や祖霊舎(それいしゃ、みたまやと呼ばれるもので、仏教における仏壇に当たるもの)に故人の死を奉告し、神棚や祖霊舎の扉を閉じて白い紙を貼ります。

枕直しの儀
遺体に白の小袖を着せたあと、北枕にして寝かせます。祭壇を設け、仏教での枕飾りのように米や水、酒などを供えます。

遺体に白の小袖を着せたあと、北枕にして寝かせます。祭壇を設け、仏教での枕飾りのように米や水、酒などを供えます。

納棺の儀
遺体を棺に納め、白い布で覆ったあとに拝礼します。

遺体を棺に納め、白い布で覆ったあとに拝礼します。

通夜祭
仏教における通夜です。神職が祭詞(祝詞)を奏上し、参列者は玉串を奉って拝礼します。

仏教における通夜です。神職が祭詞(祝詞)を奏上し、参列者は玉串を奉って拝礼します。

遷霊祭
通夜祭に続いて行います。部屋を暗くし、神職によって故人の御霊を霊璽(れいじと読み、仏教における位牌に当たるもの)に移します。

通夜祭に続いて行います。部屋を暗くし、神職によって故人の御霊を霊璽(れいじと読み、仏教における位牌に当たるもの)に移します。

葬場祭
通夜祭の翌日に行う、仏教における葬儀・告別式です。神葬祭のメインとなる儀式で、弔辞の奉呈、弔電の奉読、祭詞奏上、玉串奉奠などが行われます。故人に別れを告げる最後の機会です。

通夜祭の翌日に行う、仏教における葬儀・告別式です。神葬祭のメインとなる儀式で、弔辞の奉呈、弔電の奉読、祭詞奏上、玉串奉奠などが行われます。故人に別れを告げる最後の機会です。

火葬祭
火葬の前に火葬場で行われる儀式です。神職が祭詞を奏上し、参列者は玉串を奉って拝礼します。

火葬の前に火葬場で行われる儀式です。神職が祭詞を奏上し、参列者は玉串を奉って拝礼します。

埋葬祭
遺骨を埋葬するために行われる儀式です。遺骨を墓に納め、銘旗(故人の名前や職名などを記した旗)や花を供えます。

遺骨を埋葬するために行われる儀式です。遺骨を墓に納め、銘旗(故人の名前や職名などを記した旗)や花を供えます。

帰家祭
自宅へ戻り、塩や手水で清めます。その後、無事に神葬祭が終わったことを霊前に奉告します。 この後、神職やお世話になった人を招き、直会(なおらい)という宴を行います。

自宅へ戻り、塩や手水で清めます。その後、無事に神葬祭が終わったことを霊前に奉告します。 この後、神職やお世話になった人を招き、直会(なおらい)という宴を行います。
神道(神葬祭)に参列される際のマナー・注意点
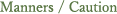
数珠は使わない
数珠はもともと僧侶がお経を読む際に数を数えるために使っていたものなので、神道では使いません。
服装は一般的な喪服で
服装は特別変わったものは必要なく、仏教の場合と同じく喪服を着用します。男女ともに色は黒で、靴下やストッキング、バッグ、靴といった小物も黒で合わせます。小物やアクセサリー類は派手なものはNGです。結婚・婚約指輪以外のアクセサリーは極力着用しないようにしましょう。
不祝儀袋の選び方と表書き
不祝儀袋にはさまざまな種類がありますが、神道では蓮の花の入っていないものを使います。水引は黒白か双銀を選びます。表書きは「御霊前」「御玉串料」などが使われます。
挨拶で「冥福」「成仏」「供養」という言葉は使ってはいけない
死に対する考え方が仏教と神道では異なるので、仏教用語は使いません。神道では、「御霊のご平安をお祈りいたします」と言葉をかけるようにしましょう。